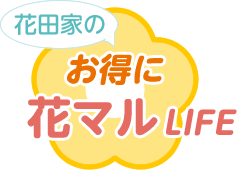リフィル処方箋ガイド:通院の負担を減らす新制度の活用法

薬をもうらうだけで毎回病院に行くのって大変だわ。
1枚の処方箋で3回薬を処方しれもらえる「リフィル処方箋」という精度があるよ
毎月の通院が時間と費用の負担になっていませんか?
慢性疾患などで定期的に通院している方なら、このような悩みをお持ちではないでしょうか。
「薬をもらうためだけに病院に行くのは時間がもったいない」
「毎回同じ薬なのに、なぜ通院が必要なのだろう」
「仕事が忙しく、平日に通院する時間を確保するのが難しい」
特に、状態が安定している慢性疾患の方にとって、単に薬を処方してもらうだけの診察は、時間的にも経済的にも大きな負担となっています。
このような悩みを抱える患者さんの負担を軽減するために、2022年に導入されたのが「リフィル処方箋」制度です。この記事では、まだあまり知られていないリフィル処方箋の仕組みや活用方法について、詳しく解説していきます。
【参考サイト:政府広報オンライン】
https://www.gov-online.go.jp/article/202411/entry-6756.html
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋制度は、2022年4月から正式に導入されました。
従来の処方箋は、1回限りの使用、次回も薬が必要な場合は再度受診が必要などの手間が必要です。
これがリフィル処方箋ですと、1枚の処方箋で最大3回まで薬を受け取ることが可能(1回目の有効期間は通常の処方箋と同様4日以内)、再診なしで同じ薬を受け取れるというものになります。
これは患者さんにとっても非常にメリットの大きな制度です。
どのような効果が期待できるかを見てみましょう。
リフィル処方箋で期待できる生活向上・節約の効果
時間の節約:往復の移動時間+待ち時間+診察時間(平均して1回の受診で1〜2時間)が削減
交通費の節約:通院のための交通費(平均して1回500円〜2,000円程度)が削減
診察料の節約:再診料や各種管理料などの医療費(1回あたり数百円〜数千円)が削減
他にも、以下のような生活の質(QOL)の向上が期待できます。
・仕事や家事などの日常生活に集中できる
・体調不良時以外の不要な通院によるストレス軽減
・薬が切れるリスクの減少
・天候や体調に左右されず薬を確保できる安心感
医療機関や薬局、社会全体にもリフィル処方箋はメリットが期待できる
患者さんだけでなく、医療機関や社会にもいろいろとメリットが期待できます
【医療機関のメリット】
・再診のための診察時間が減少し、新患や急性期患者への対応が充実
・事務作業や文書管理の効率化
・薬局では患者さんの継続的なフォローが可能に
【社会全体のメリット】
・医療資源の効率的な配分
・医療費の適正化
・患者の通院による環境負荷(交通機関のCO2排出など)の軽減
・感染症流行時の医療機関での接触機会減少
リフィル処方箋の注意点
ただし、どんな患者さんでもこのリフィル処方箋が適用されるわけではありません。また、同じ疾患でも患者さんの状態によっては適用される場合と、されない場合があったりもします。
受診する医療機関や担当医師の方針によっても適用条件は異なる場合があります。
そこでリフィル処方箋の利用を希望する場合は、まず担当医に相談することが第一歩です。以下のようなアプローチが効果的です
医師や病院への相談のタイミング
・定期受診時に直接相談する
・薬の処方内容が安定してきたタイミングで相談する
・次回の診察予約を取る際に看護師や受付に事前に確認してみる 等
また医師への伝え方ですが、例えば次のような伝え方はどうでしょうか?
「この薬はリフィル処方箋で処方していただくことは可能でしょうか?」
「最近の検査結果も安定していて、同じ薬を継続して服用していますが、リフィル処方箋の対象になりますでしょうか?」
「仕事の都合で通院が難しいため、リフィル処方箋を検討していただけないでしょうか?」
リフィル処方箋制度の要点まとめ
リフィル処方箋は、一定期間内であれば再診なしで同じ処方薬を繰り返し受け取れる制度です。
最大3回までを同じ処方箋で、薬を受け取ることが可能になります。
ただし、全ての医療機関で対応しているわけではありませんので、気になる方は一度医師に相談してみてください。
リフィル処方箋制度の注意点
リフィル処方箋制度は2022年4月に導入されたばかりの比較的新しい制度です。今後、まだまだ制度が変更される可能性があります。
ぜひ最新の情報などを確認し、医師や病院・クリニックに必ず確認をとるようにしましょう。
【参考サイト:政府広報オンライン】
「リフィル処方箋」を知っていますか?
【参考サイト:厚生労働省】
長期処方・リフィル処方の活用について